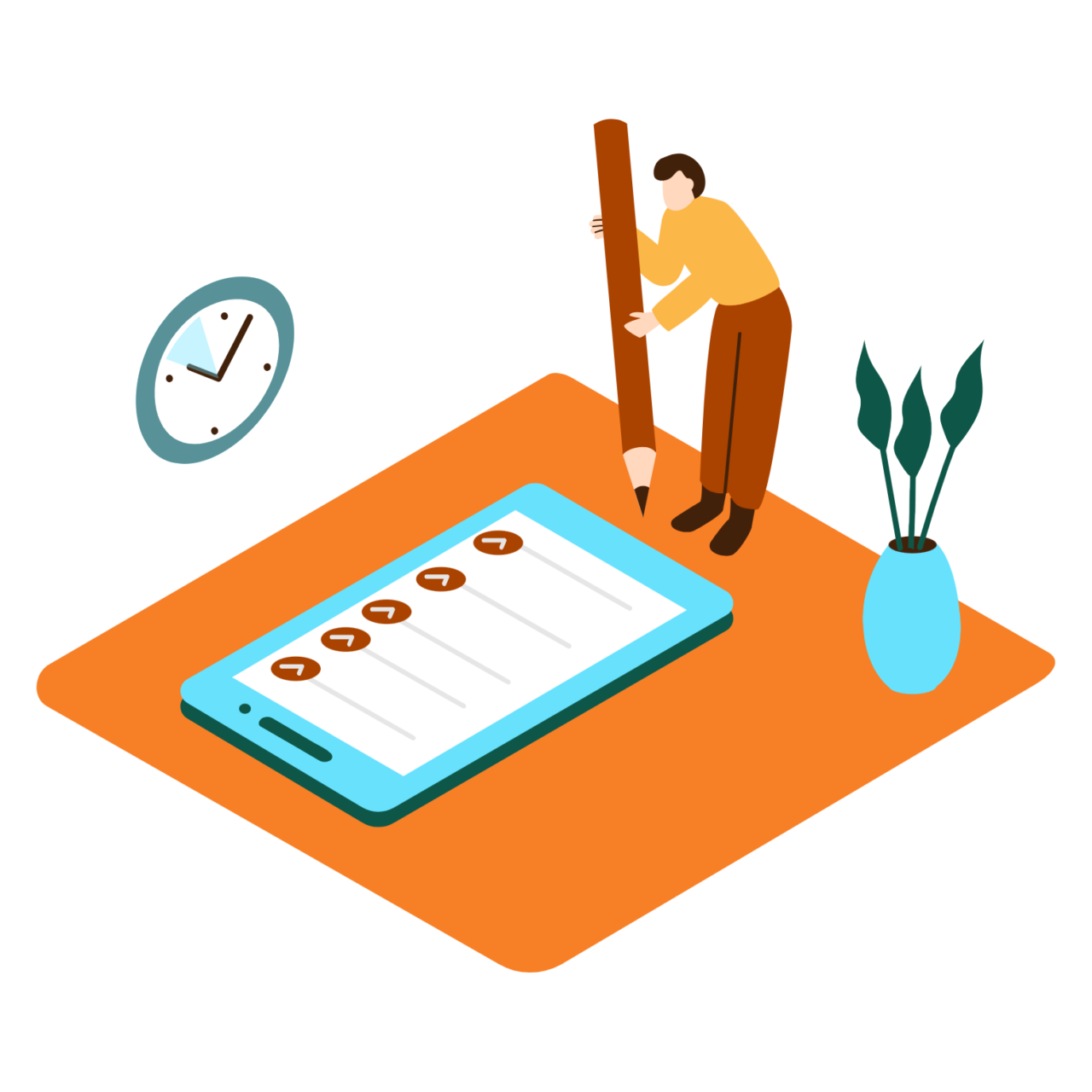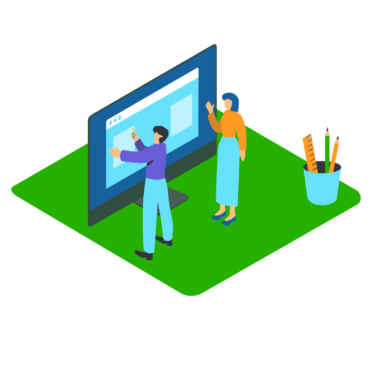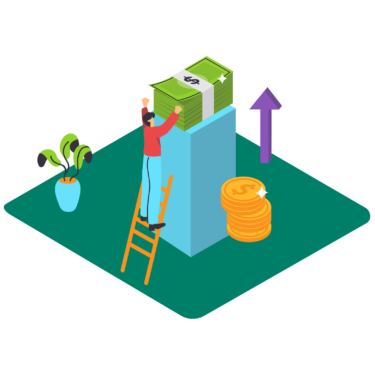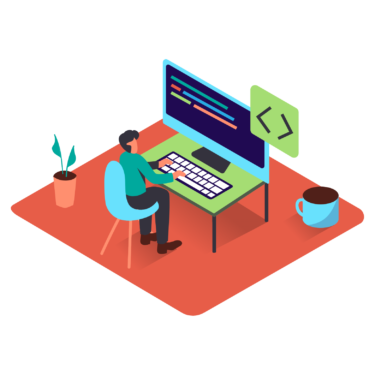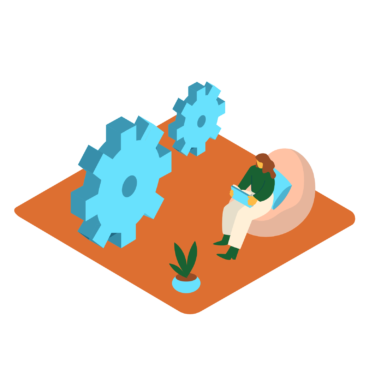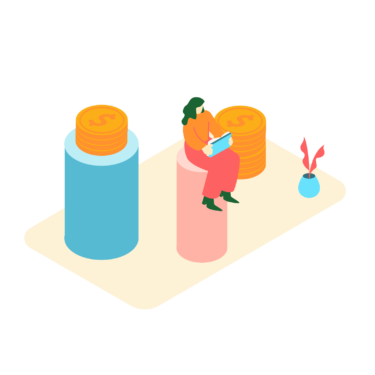「ウォーターフォール開発って、なんだか古そうなイメージだけど、今も使われているの?」
「最近よく聞くアジャイル開発と、何が違うの?」
ソフトウェア開発の世界には、プロジェクトを成功に導くための、いくつかの**「開発モデル(進め方の型)」が存在します。その中でも、最も古くから存在し、今なお大規模なシステム開発の現場で採用されている、伝統的で王道な手法。それが「ウォーターフォール開発」**です。
一言でいうと、ウォーターフォール開発とは**「『要求定義』→『設計』→『開発』→『テスト』といった、開発の各工程(フェーズ)を、滝(Water-fall)の水が上から下に流れるように、順番に、そして後戻りすることなく進めていく、計画重視の開発手法」**のことです。
この記事では、IT知識ゼロの初心者の方でも、ウォーターフォール開発の本質がスッキリと理解できるように、**「家づくり」**に例えながら、わかりやすく徹底的に解説していきます。
-
ウォーターフォール開発の具体的な「工程」
-
そのメリットと、現代におけるデメリット
-
ライバルである「アジャイル開発」との決定的な違い
-
どんなプロジェクトに、ウォーターフォールは向いているのか
ウォーターフォール開発の基本的な「工程」:後戻りは許されない、一本道

ウォーターフォール開発の最大の特徴は、各工程を、順番に、一つずつ完了させてから、次の工程に進むという点にあります。原則として、一度終わった工程に、後戻りすることは想定されていません。
この厳格なプロセスを、家づくりに例えて見ていきましょう。
1. 要求定義(企画):「どんな家に住みたいか?」を決める
-
やること:施主(顧客)と、建築家(コンサルタントやSE)が、徹底的に話し合います。「家族4人で住みたい」「日当たりの良いリビングが欲しい」「地震に強い構造にしてほしい」「予算は3000万円以内で」といった、**家に対するあらゆる要望(要求)**を聞き出し、文書(要求定義書)にまとめます。
-
成果物:要求定義書
-
ポイント:ここで**「何を作るか」を、完全に、そして最終的に**決定します。この後の工程で、「やっぱり子供部屋をもう一つ追加したい」といった、根本的な変更は原則できません。
2. 外部設計(基本設計):「家の間取り図」を描く
-
やること:要求定義書をもとに、家の**「外から見える部分」**の設計を行います。間取り、部屋の広さ、ドアや窓の配置、外観のデザインなどを決め、設計図(基本設計書)を作成します。
-
成果物:基本設計書
-
ソフトウェア開発では:ユーザーが直接触れる画面のレイアウト(UI設計)や、システムの機能一覧などを定義します。
3. 内部設計(詳細設計):「家の内部構造」を決める
-
やること:基本設計書をもとに、家の**「中身の見えない部分」**の、詳細な設計を行います。柱の太さや材質、電気の配線ルート、水道管の配置といった、職人(プログラマー)が実際に工事(開発)を進めるための、非常に詳細な指示書を作成します。
-
成果物:詳細設計書
-
ソフトウェア開発では:プログラムの内部構造(クラス設計)、データの処理方法(アルゴリズム)、データベースのテーブル設計などを、プログラマーが迷わずコードを書けるレベルまで、細かく定義します。
4. 開発(プログラミング):「設計図」をもとに家を建てる
-
やること:大工さんや職人(プログラマー)が、詳細設計書という完璧な指示書だけを頼りに、ひたすら家を建てていきます(コーディング)。この段階で、プログラマーが「この柱、もう少し太い方がいいのでは?」と、勝手に設計を変更することはありません。
-
成果物:プログラムコード
5. テスト:「家の欠陥」がないか、徹底的にチェックする
-
やること:家が完成したら、様々なテストを行います。
-
単体テスト:ドアはちゃんと開くか?蛇口から水は出るか?(プログラムの小さな部品(モジュール)ごとのテスト)
-
結合テスト:お風呂のお湯を沸かしながら、キッチンで料理をしても、ブレーカーは落ちないか?(部品同士を組み合わせたときのテスト)
-
総合テスト:家族4人が、実際に1日暮らしてみて、要求通り、快適に、そして安全に生活できるか?(システム全体のテスト)
-
-
成果物:テスト報告書
6. 導入・運用:「引き渡し」と、その後のメンテナンス
-
やること:すべてのテストをクリアしたら、ついに施主(顧客)に家を引き渡します(リリース・導入)。そして、住み始めてから発生した不具合(雨漏りなど)に対応する、アフターサービス(運用・保守)が始まります。
ウォーターフォール開発のメリット:「計画通り」に進める安心感
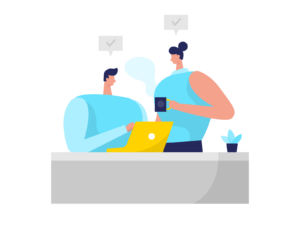
この一見、堅苦しい手法が、なぜ長年にわたって使われ続けてきたのでしょうか。それには、明確なメリットがあるからです。
計画が立てやすく、進捗管理が容易
最初にすべての工程と作業内容を定義するため、全体のスケジュールや、必要な人員、コストの見積もりが、非常に立てやすいです。各工程の終わりに、明確な成果物(設計書など)が完成するため、「今、プロジェクト全体の何%が終わっているか」という進捗状況が、誰の目にも分かりやすいです。
品質を確保しやすい
各工程を、専門の担当者(設計のプロ、テストのプロなど)が、じっくりと時間をかけて担当します。また、前の工程が完璧に終わっていることを前提に次に進むため、手戻りが少なく、成果物の品質を高く保ちやすいです。
大規模・大人数のプロジェクトに向いている
作業が明確に分担されているため、何十人、何百人という大人数が関わる大規模なプロジェクトでも、統制を取りやすいです。
ウォーターフォール開発のデメリット:「変化」への弱さ

一方で、ウォーターフォール開発には、現代のビジネス環境において、致命的とも言える弱点が存在します。
仕様変更に、極めて弱い
最大のデメリットです。家を建て始めてから、「やっぱりリビングを2階にしたい」と言われても、もう手遅れですよね。ウォーターフォール開発も同じで、後の工程で仕様変更が発生すると、設計の工程まで遡って、すべてやり直す必要があり、莫大な手戻りコストと、スケジュールの遅延が発生します。
開発期間が、長期化しやすい
すべての工程を順番に進めるため、実際に動くものが完成するのは、プロジェクトの最終盤になります。数ヶ月、時には数年にわたる開発期間中、顧客は完成品を目にすることができません。
完成品が、時代遅れになるリスク
開発期間が長いため、1年前に立てた計画に基づいて開発を進めていたら、リリースする頃には、市場のニーズや、競合の状況が、すっかり変わってしまっていた…という悲劇が起こり得ます。
ライバルの登場:アジャイル開発との決定的な違い
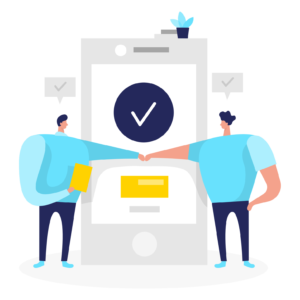
このウォーターフォールの「変化への弱さ」を克服するために生まれたのが**「アジャイル(Agile)開発」**です。
| ウォーターフォール開発 | アジャイル開発 | |
| 思想 | 計画重視 | 変化への対応を重視 |
| 開発単位 | 一つの巨大な塊(プロジェクト全体) | 小さな機能の塊(スプリント/イテレーション) |
| 進め方 | 一直線(後戻りしない) | 反復(短いサイクルを何度も繰り返す) |
| 仕様変更 | 原則NG | 大歓迎 |
| 顧客の関わり方 | 最初と最後だけ、深く関わる | 常に、開発チームの一員として関わる |
| 例えるなら | 巨大な豪華客船を、完璧な設計図通りに、数年かけて建造する | 小さなボートで、まず対岸に渡ってみて、そこから次の目的地を考えながら、何度も航海を繰り返す |
これにより、顧客は早い段階で動くものに触れることができ、そのフィードバックを、次のサイクルにすぐに反映させることができます。
「アジャイル開発って、最近よく聞くけど、一体何のこと?」「スクラムとか、スプリントとか、カタカナが多くてよくわからない…」「ウォーターフォイル開発と、どっちがいいの?」 現代のソフトウェア開発、特に変化の激しい[…]
まとめ:ウォーターフォールは「終わった」のか?

「じゃあ、もうウォーターフォールは古くて、アジャイルが最高なの?」
答えは**「No」です。両者には、それぞれ得意なプロジェクト**があります。
【ウォーターフォール開発が向いているプロジェクト】
-
仕様や要件が、最初から明確に決まっているもの
-
銀行の勘定系システムや、官公庁のシステムなど、法律や制度で、作べき機能が厳密に決まっているプロジェクト。
-
-
品質や安全性が、何よりも重視されるもの
-
人命に関わる医療システムや、社会インフラを制御するシステムなど、絶対に失敗が許されない、ミッションクリティカルなプロジェクト。
-
-
大規模で、変更が少ないもの
【アジャイル開発が向いているプロジェクト】
-
仕様や要件が、まだ固まっていないもの
-
世の中にない、新しいWebサービスや、ユーザーの反応を見ながら改善していきたい、スマートフォンアプリの開発。
-
-
市場投入までのスピードが、最優先されるもの
プログラミング初心者として、まずこの伝統的なウォーターフォール開発の一連の流れを理解しておくことは、あらゆるシステム開発の基本となる「工程」を、体系的に学ぶ上で、非常に重要な知識となるでしょう。
将来性のあるIT業界で、専門スキルを身につけて活躍したいでも、 何から勉強すればいいの? 実務経験ゼロで本当に採用される?」膨大な求人情報の中から、自分に合った企業をどうやって見つけるの? 現代において[…]