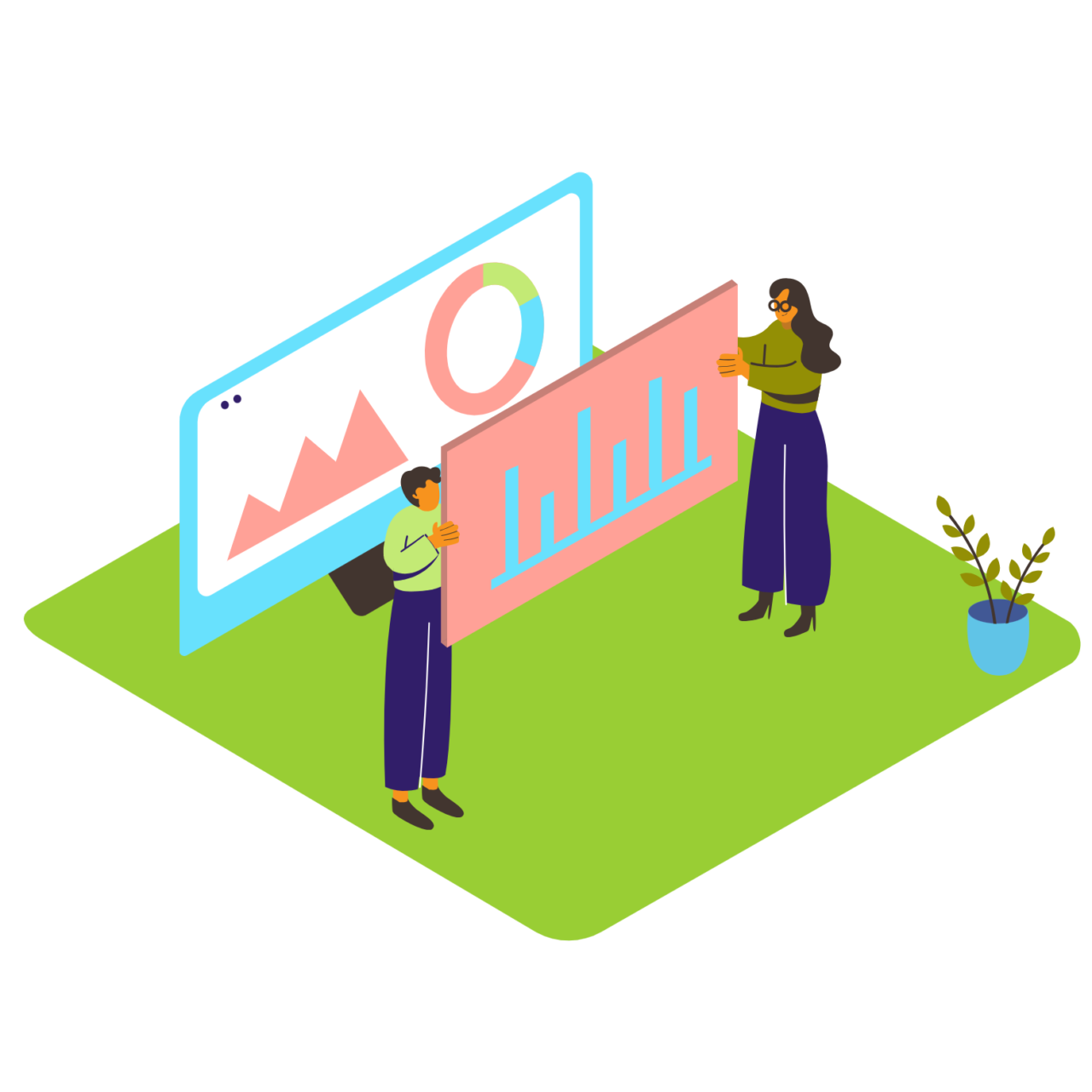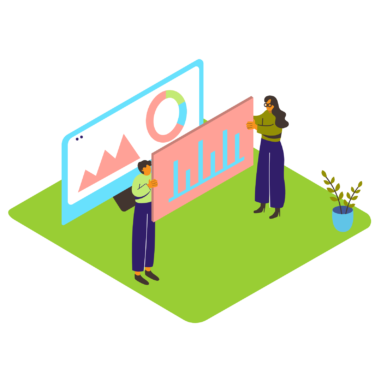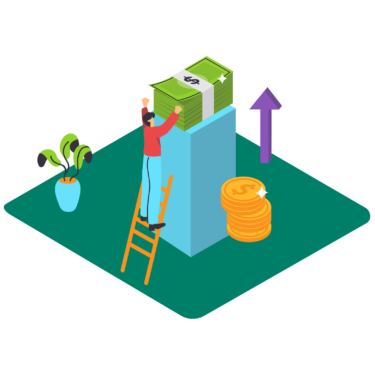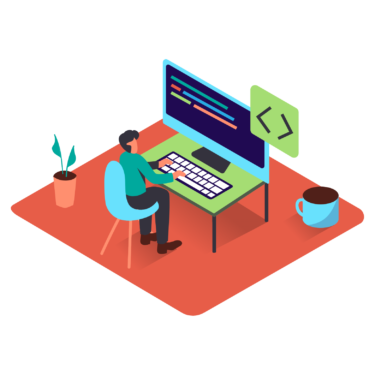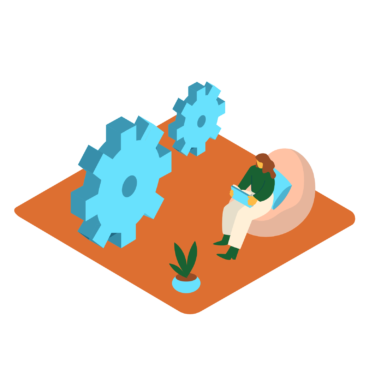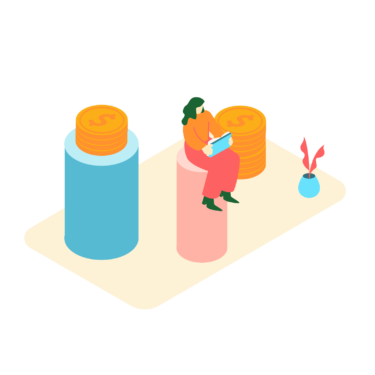「プラットフォームエンジニアリングっていう、新しい言葉も出てきたけど、何が違うの?」
現代のソフトウェア開発の世界では、**「いかに速く、そして安全に、価値あるソフトウェアをユーザーに届け続けるか」**という課題が、これまで以上に重要になっています。
この課題を解決するための、2つの非常に重要で、密接に関連する考え方。それが**「DevOps」と、その進化形とも言える「プラットフォームエンジニアリング」**です。
この記事では、IT知識ゼロの初心者の方でも、これらのモダンな開発アプローチの本質がわかるように、**「ラーメン屋さんの厨房」**に例えながら、わかりやすく徹底的に解説していきます。
-
DevOpsが生まれた背景と、その目的
-
プラットフォームエンジニアリングの役割
-
両者の決定的な違いと、その深い関係性
-
これらを支える重要な技術(CI/CD, IaCなど)
物語の始まり:DevOpsが生まれる前の「壁」
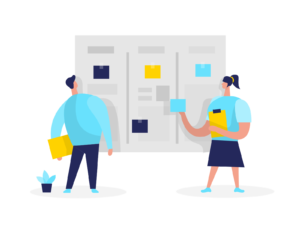
DevOpsの価値を理解するには、まず、それがなかった時代の開発現場が、どれほど非効率だったかを知る必要があります。
かつてのソフトウェア開発の現場には、2つのチームの間に、高く、そして厚い**「壁」**が存在していました。
-
開発(Development)チーム
-
役割:新しい機能を追加したり、バグを修正したりと、**「変化」**を生み出すのが仕事。プログラマーが中心。
-
口ぐせ:「早く新しい機能をリリースして、ユーザーを喜ばせたい!」
-
-
運用(Operations)チーム
-
役割:既存のシステムが、24時間365日止まらないように、**「安定」**を守るのが仕事。インフラエンジニアが中心。
-
口ぐせ:「勝手に新しい変更を加えるな!システムが不安定になったらどうするんだ!」
-
開発チームは「変化」を求め、運用チームは「安定」を求める。この正反対の目標を持つ両者は、しばしば対立し、お互いに責任をなすりつけ合っていました。
開発チームが作ったソフトウェアを、壁の向こうの運用チームに「あとはよろしく!」と投げ渡す。運用チームは、中身がよくわからないソフトウェアの運用に苦労し、問題が起きれば「開発の作ったものが悪い!」と非難する。
革命の到来:DevOpsという「壁の破壊」
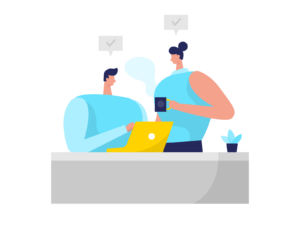
この非効率な状況を打破するために生まれたのが**「DevOps」**という考え方(文化・哲学)です。
DevOpsは、Development(開発)と Operations(運用)を組み合わせた造語で、その目的は、「開発チームと運用チームが、お互いに協力し合い、コミュニケーションを密に取ることで、『壁』を取り払い、ソフトウェアの開発からリリース、運用までの一連のプロセスを、迅速かつ自動化し、ビジネスの価値を、より速く、より頻繁に、そして安全にユーザーに届けること」です。
【ラーメン屋さんで例えるDevOps】
-
DevOps以前:調理担当(開発)と、配膳・ホール担当(運用)が完全に分断。調理担当は、ひたすらラーメンを作り、カウンターに置くだけ。ホール担当は、それがどんなラーメンかよくわからないまま、お客さんに運び、クレーム対応に追われる。
-
DevOps導入後:調理担当とホール担当が、一つのチームとして協力。
-
ホール担当が「お客さんは、もっと熱々のスープを求めている」とフィードバックすれば、調理担当はすぐに調理法を改善する。
-
調理担当は、運びやすいように、お盆の大きさまで考えてラーメンを作る。
-
注文から提供までの流れを、全員で見直し、無駄な動きを徹底的に排除(自動化)する。
→ 結果として、より美味しく(高品質)、より熱々の(価値ある)ラーメンを、より速く(迅速)、お客さんに届けられるようになります。
-
DevOpsを支える重要な技術

DevOpsという文化を実現するために、いくつかの重要な技術が使われます。
-
CI/CD (継続的インテグレーション / 継続的デリバリー)
-
ソフトウェアの変更(コードの修正など)を、自動的にテストし、問題がなければ、いつでもリリースできる状態に保つ仕組み。開発からリリースまでのプロセスを、可能な限り自動化します。
-
-
IaC (Infrastructure as Code)
-
サーバーやネットワークといったインフラの構成を、手作業ではなく、プログラミングコードで管理する手法。これにより、インフラ構築も自動化でき、開発チームもインフラの管理に関わりやすくなります。
-
-
マイクロサービスアーキテクチャ
-
一つの巨大なアプリケーションではなく、小さく独立したサービスの集合体としてシステムを構築する設計。これにより、サービスごとに独立して、迅速な開発とデプロイが可能になります。
-
さらなる進化:プラットフォームエンジニアリングの登場
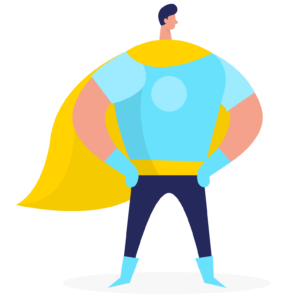
DevOpsの導入により、開発チームと運用チームの壁は取り払われました。
開発者自身が、CI/CDやIaCといったツールを使い、インフラの構築や、アプリケーションのデプロイまでを担うようになったのです。
しかし、ここで新たな問題が生まれます。
それは、**「開発者の認知負荷(Cognitive Load)の増大」**です。
本来、アプリケーションの機能開発に集中したいはずの開発者が、
「AWSのこのサービスの設定はどうすればいいんだっけ…」
「Kubernetes(コンテナ管理ツール)のYAMLファイル、書き方が複雑でわからない…」
「CI/CDパイプラインの構築が、難しすぎる…」
といった、インフラや運用に関する、複雑で専門的な知識まで、すべてを習得しなければならなくなったのです。
この問題を解決するために、DevOpsの進化形として登場したのが**「プラットフォームエンジニアリング」**です。
一言でいうと、プラットフォームエンジニアリングとは、「開発者(DevOpsチーム)が、インフラや運用の複雑な部分を意識することなく、セルフサービスで、簡単かつ安全にアプリケーションを開発・デプロイできるための『共通基盤(プラットフォーム)』を、専門のチームが構築・提供するアプローチ」のことです。
【ラーメン屋さんで例えるプラットフォームエンジニアリング】
DevOpsを導入したラーメン屋さんでは、調理担当(開発者)も、ホールのこと(運用)を考えなければならず、大忙しです。
そこで、店長は**「厨房設備専門チーム(=プラットフォームエンジニアリングチーム)」を結成します。
このチームの仕事は、ラーメンを作ることではありません。彼らのミッションは、「調理担当が、最高のラーメンを、最も効率よく作れるための、究極の厨房環境(プラットフォーム)を提供すること」**です。
-
ボタン一つで、最適な温度のお湯が、最適な量だけ出る給湯システムを開発する。
-
麺の種類を選ぶだけで、最適な茹で時間で自動的に麺を茹で上げてくれる、全自動の麺茹で機を導入する。
-
トッピングを、間違いようがないように、決められた順番でしか置けないような、専用のトレーを設計する。
これにより、調理担当(開発者)は、もはや**「お湯の温度は?」「麺の茹で時間は?」といった、面倒なことを一切気にする必要がなくなります。** ただ、ラーメンの味付けという、最も創造的で、本質的な作業に集中すれば、誰でも、安全に、そして素早く、高品質なラーメンを提供できるようになるのです。
DevOpsとプラットフォームエンジニアリングの違いと関係性

| DevOps | プラットフォームエンジニアリング | |
| 目的 | 開発と運用の壁を壊し、プロセスを効率化する | 開発者の認知負荷を下げ、体験を向上させる |
| 対象 | 文化・プロセス・人 | ツール・サービス・基盤 |
| 視点 | 「How」(どうやって、開発から運用までをスムーズに行うか) | 「What」(何を、開発者に提供すれば、彼らの仕事が楽になるか) |
| 関係性 | 哲学・文化 | DevOpsの哲学を、より大規模かつ効率的に実現するための「実践手法」 |
重要なのは、プラットフォームエンジニアリングは、DevOpsを否定したり、代替したりするものではない、ということです。
むしろ、DevOpsという文化が成熟した結果、その理想を、より多くの開発者が、より簡単に実現できるようにするために生まれた、**「DevOpsの進化形・実践形」**と捉えるのが、最も正しい理解です。
まとめ

DevOpsとプラットフォームエンジニアリング。
この2つのキーワードは、現代のソフトウェア開発を理解する上で、欠かすことのできない両輪です。
-
DevOpsは、開発と運用が協力し合う**「文化」**。
その目的は、ビジネス価値を、より速く、安全に届けること。 -
プラットフォームエンジニアリングは、そのDevOps文化を、開発者が簡単に実践できるようにするための**「基盤」を提供する「実践手法」**。
その目的は、開発者の体験を向上させ、本来の創造的な仕事に集中させること。
あなたがこれからプログラミングを学び、開発の現場に入ったとき、そこにはCI/CDパイプラインが整備され、ボタン一つでデプロイできる、素晴らしい「プラットフォーム」が用意されているかもしれません。
その裏側には、DevOpsという文化を根付かせ、プラットフォームエンジニアリングという実践で、開発者の仕事を楽にしようと奮闘している、多くのエンジニアたちの努力がある。そのことを知っておくだけで、日々の開発業務が、より深く見えてくるはずです。